
NISAやiDeCoはやっているけど、もっと投資がしたい!

将来に向けて「金のなる木」を育てたい!
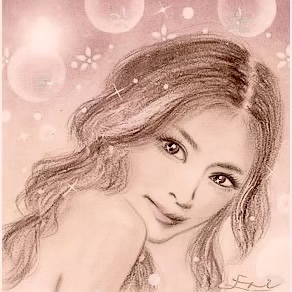 ajico
ajicoそれなら米国ETFの積立投資がオススメです!
私は米国ETFを2020年8月からSBI証券で積み立てています。
「つみたてNISA」(※2025年現在はSBI証券でNISA運用中)と「iDeCo」は楽天証券で積立していますが、外国株式や海外ETFの購入に関してはSBI系列の方が有利な点が多いのでこちらを利用しています。
これから米国ETF投資を始めたいと思っている方向けに、SBI証券で買付するメリットや買付の仕方を紹介していきたいと思いますので、興味のある方はぜひ参考にしてみてくださいね。
米国ETFとはどんなもの?
米国ETFとは、米国株式市場に上場している投資信託のことで、一般の投資信託との違いは、上場しているためリアルタイムでの売買が可能というところです。
米国だけでなく米国以外の株式や債券にも投資することができます。
米国の株式市場には世界中から優良な投資商品が集まってくるため、米国ETFを使えば世界中の優良金融商品に投資することが可能になります。
SBI系列で海外ETF投資をするメリット3点
住信SBIネット銀行の外貨積立によって為替を気にせずドルの積み立てができる
住信SBIネット銀行の外貨積立は、その積立方法を「毎日」「毎週」「毎月」から選ぶことができます。
私はなるべく時間分散させることで為替リスクを抑えるために、現在は「毎日」1万円ずつの積立をしていますが、たとえば「1ドル=105円を超えたら積立を自動停止するといった設定も可能です。
住信SBIネット銀行のドル転コストは4銭(積立なら2銭)と激安!
住信SBIネット銀行では、ドル買付時の為替コストは1ドルあたりわずか4銭で、外貨積立を利用すれば2銭まで下げることができます。
他社はほとんどが25銭であるため、この差は非常に大きいですね。
証券会社で唯一、米国ETFの定期買付設定ができる
証券会社の中で、海外ETFの定期買付設定ができるのはSBI証券だけです。
他の証券会社では、都度購入しなければならないため手間がかかったり、忘れたりしてしまいますが、SBI証券の定期買付では一度設定しておきさえすればあとは自動で積み上がっていくので非常に便利です。
また、海外ETFや外国株式投資では、以前は一度に1,111ドル以上を購入しないと手数料負けしてしまいましたが、今現在は最低手数料が撤廃されたことで積立投資が実践しやすくなりました。

まとめ
低コストなETFを定期買付できれば、ドルコスト平均法によりリスク回避も可能で、まさに最強の投資法になると思います。
今後の計画としては、数年はキャピタルゲイン目的で分配金を再投資しながら資産拡大を目指し、その後は増えたETFからの分配金をインカムゲインとして受け取り、今の収入の半分くらいでも今と同じ水準の生活ができるサイドFIREを目指しています!!
サイドFIREの魅力については投資家人気Youtuber「両学長」のこちらの動画をご覧くださいませ。👇
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました‼

